| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Category
Resent Update
- TeachersOnline制作日記⑤ 教育キーワード検定
- はじめまして
- 電子書籍と本ははたして共生可能なのか?
- 新・社長ブログ開設のお知らせ
- 新刊が発売されます
- 「Teachers Online」が読売新聞で紹介されました
- ライターズCafe
- 株式会社マコル 公式Webサイトが開設
- 新年のごあいさつ
- 今年もお世話になりました
Back Number
- 記事一覧
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
Comments
漢字とひらがな
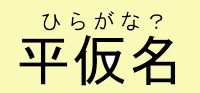 先日、あるクライアントさんと「展示会のパネル制作」について打合せをしたときの話です。
先日、あるクライアントさんと「展示会のパネル制作」について打合せをしたときの話です。
そのパネルは、小学生から大人まで幅広い人が見るモノなのですが、難しい漢字にルビ(ふりがな)を振るかどうかで、ちょっとした議論になりました。
「小学生が見るのだから、より多くの漢字にルビを振った方がよい」という意見がある一方で、「あまりルビだらけになると、大人は馬鹿にされたように気分になるのでは」との意見もありました。
これは本づくりやWebサイト制作にも共通した問題で、「日本語のユニバーサルデザイン化」は実に難しいものです。
ただ、最近はお気づきの方もいるかもしれませんが、日本語にルビが振られたり、漢字が平仮名表記になったりしているケースが増えています。
新聞や雑誌などを見ても、昔は漢字で書いていた言葉が、平仮名で表記されている例を比較的簡単に見つけることができます。
理由はさまざまなですが、指摘の一つに「日本人の漢字能力の低下」があります。すなわち、若者を中心に難しい漢字を読めない人が増えているというのです。
背景には、パソコン・携帯電話の普及や「ゆとり教育」の影響があるのでしょうが、字幕を付ければ付けるほど、読めない人が増えるというジレンマもあり、実に難しい問題です。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.con-text.co.jp/mt/mt-tb.cgi/40
